This post was originally published on this site.
今回、目安を上回る大幅な引き上げが相次いだことなどについて、最低賃金に詳しい法政大学経営大学院の山田久教授に話を聞きました。
Q.全都道府県で初めて1000円を超えた。
A.物価の高騰で労働者は生活が厳しい状況になっている。
労働者の生活水準の維持という点で最低賃金の本来の意義から見ても基本的には前向きに評価できる。
ただ、日本の水準は国際的に見て特にヨーロッパ諸国に比べるとかなり低い状況だ。
まだまだ通過点であり、さらなる引き上げが必要だ。
Q.目安を大幅に上回る引き上げが相次いだ。
A.最低賃金の引き上げの必要性が全体的に共有されてきている。
人手不足が非常に深刻化していて、県境を超えて最低賃金の高い地域に人が動くということが起こっている。
そうした中で、人材を確保していくためには思い切って引き上げていかないといけない状況にあり、目安より高い形で決着するところが出てきているとみられる。
Q.引き上げによる影響は?
A.労働者側にとっては生活に対してプラスということで望ましい動きだと思う。
一方で企業にとっては人件費がかなり増えることになる。
近年、最低賃金を引き上げてきたこともあって、特に中小・零細企業では人件費の負担が非常に重くのしかかり経営が厳しくなっているというのが今の実態だ。
Q.新しい最低賃金の適用を来年にする県も出たが…。
A.人材確保のため大幅に引き上げをせざるをえないというのが現状だが、その一方で人件費の負担は増えて経営的に厳しい中小企業に配慮するという意味では、妥協的な対応といえる。
労使の溝が埋まらなかった結果だと思うので、全体のスケジュールを前倒しして十分な時間をかけて議論し、これまでどおりの時期に引き上げるのが望ましいのではないか。
国の目安の意味がだんだん薄れてきているという声もあるが、目安というのはあくまで目安で、それぞれの都道府県の状況を踏まえて独自に決めていくっていうのは、本来のあり方とも言える。
ただ、引き上げ額が目安からかい離すればするほど、地方の最低賃金の審議会の説明責任は問われるようになる。
Q.今後については。
A.最低賃金の額が低いと人が集まりにくいので、全体で見ると底上げの圧力ということになっていくのではないか。
ただ、重要なのは最低賃金を大きく引き上げていくことになると、やはり中小企業には大きな負担がかかってくるので、政府や都道府県などが中小企業の生産性の向上に対しての支援をきめ細かにやっていく。
そうして底上げしやすい環境を整えていくことが非常に重要なことだと考える。








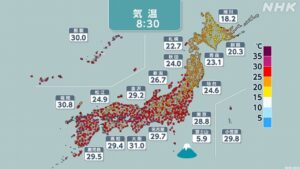
コメント