This post was originally published on this site.
小中学校や高校で教える内容や目標などを定めた「学習指導要領」は、おおむね10年ごとに改訂されています。
去年12月、文部科学省から諮問を受けた中教審の特別部会が、2030年代の学習指導要領の改訂を進めていて、5日、これまでの議論の論点をまとめました。
それによりますと、予測困難な時代を生きる子どもたちには、生きて働く確かな知識の習得やみずから学びに向かう力、それに生成AIなどのデジタル技術の進展に対応する情報活用能力の育成が必要だとしています。
このうち情報活用能力については、小学校では「総合的な学習の時間」に位置づけて、探究的な学習と連携させることや、中学校では、現在の「技術・家庭科」を分離して、「情報・技術科」(仮称)を新たに設けるとしています。
また、不登校や特定分野への特異な才能など子どもの特性や個性に応じた多様な学びを重視するとして、一人一人の実態に配慮したカリキュラムを編成できる仕組みを新たに設けるとしています。
また、こうした方針を持続可能にするため、教員と子どもの双方に「余白」を作り出す柔軟な教育課程が必要だとしています。
中教審の特別部会は今月下旬以降、個別の教科ごとの具体的な検討を進め、来年度中に答申することにしています。
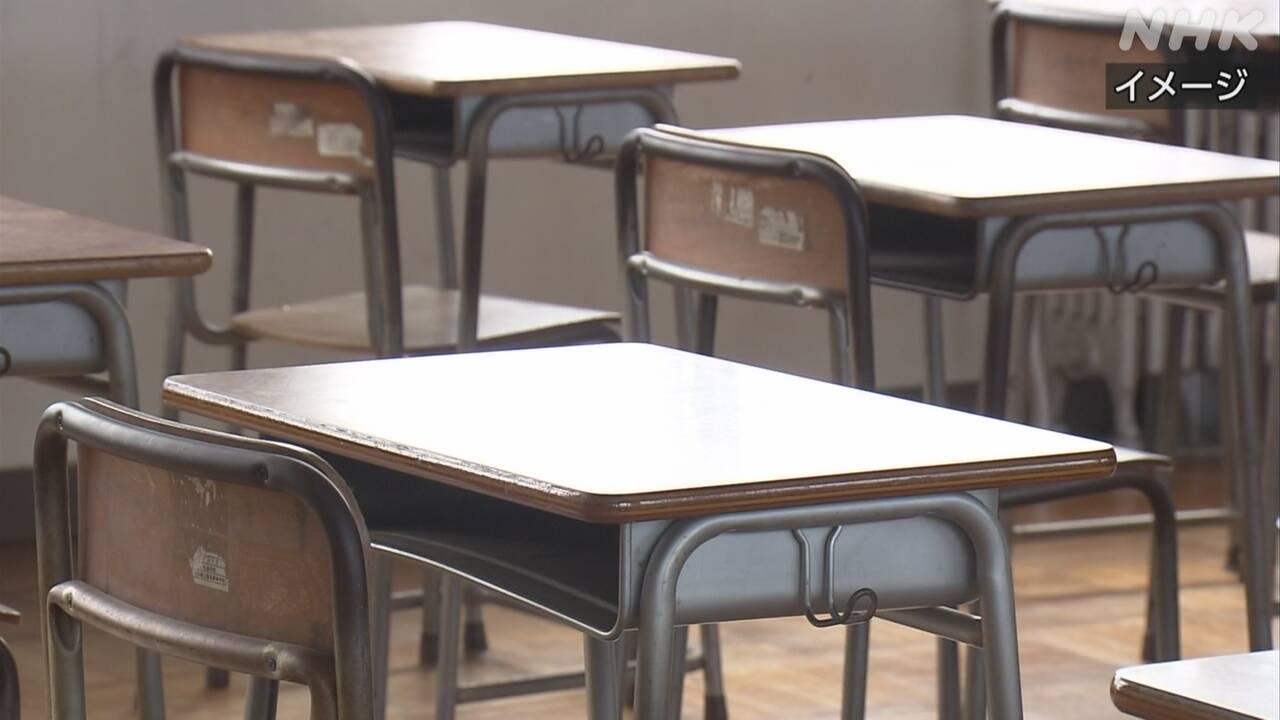







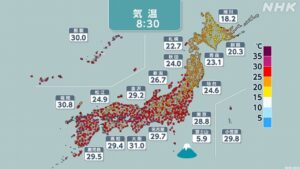
コメント